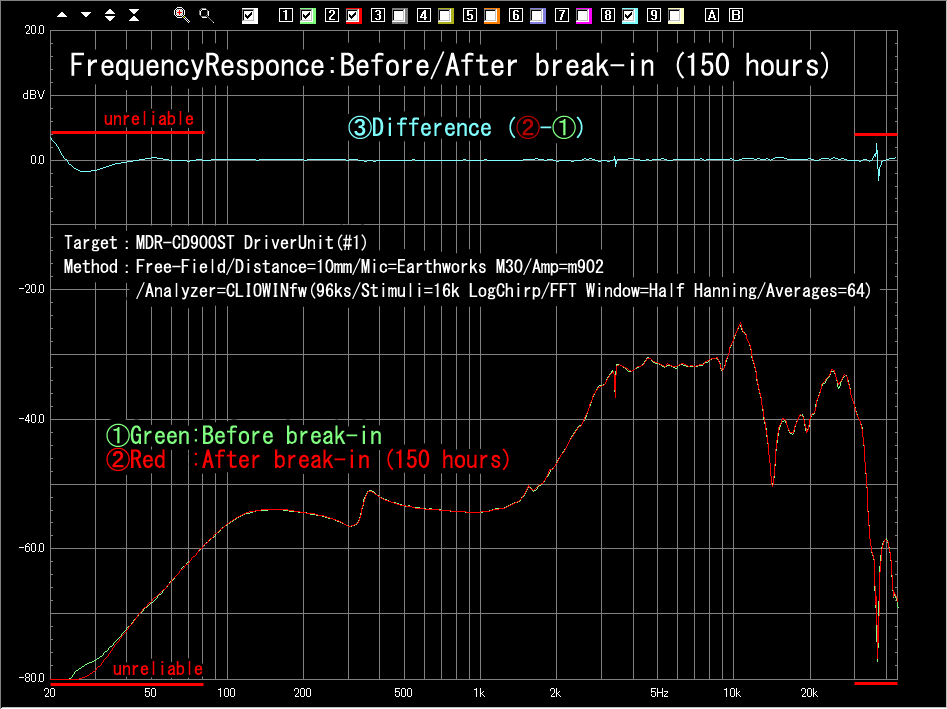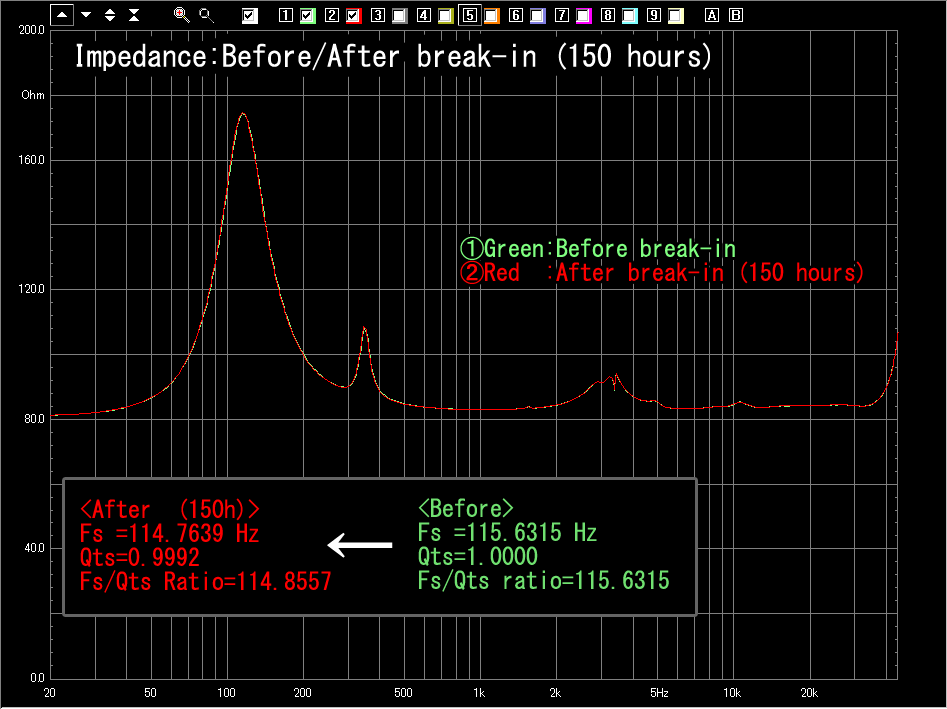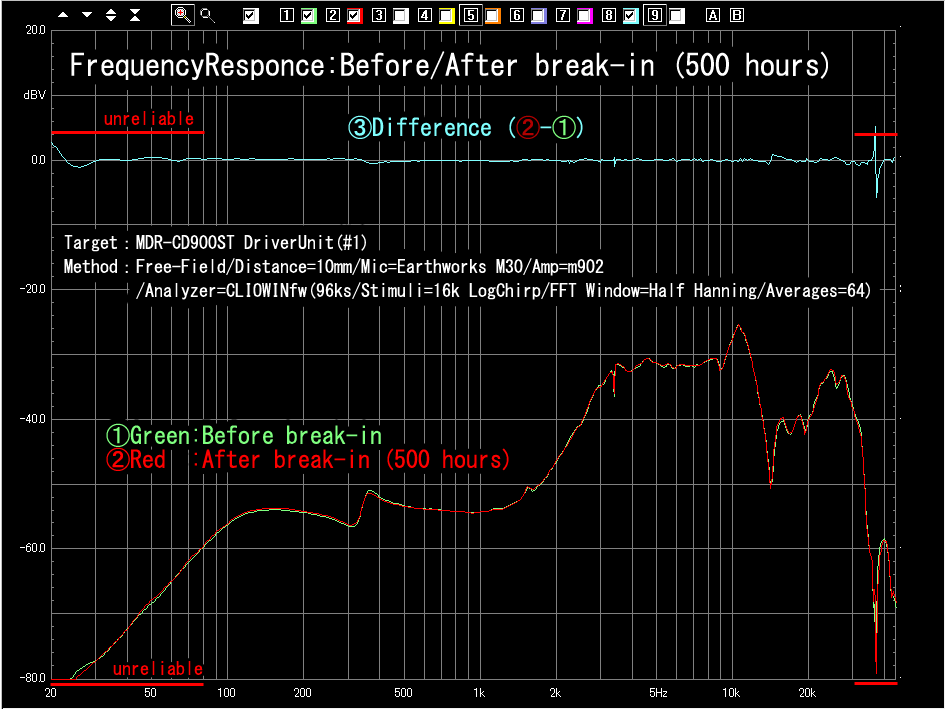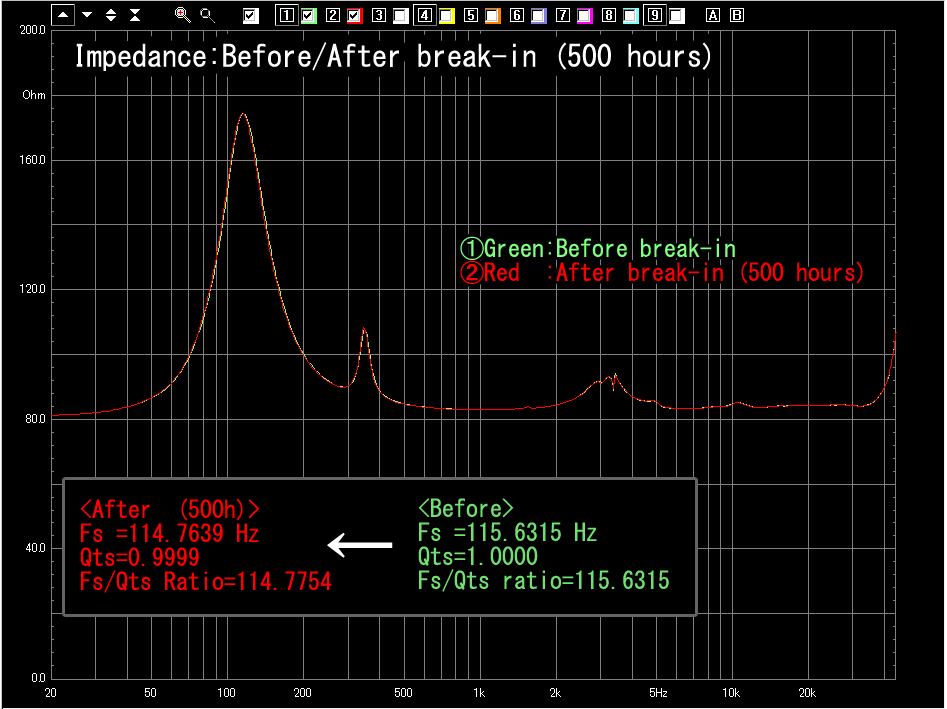| �y�P�D�T�v�z MDR-CD900ST�̃h���C�o�[�P�̂ɂ��āA�G�[�W���O�i�u���[�N�C���j�̌��ʂ��ώ@�����Ă݂�B�i150���ԁj
150���ԂƂ������[�Ȑ����̗��R�ɂ��ẮA����300���Ԃ��炢��낤���Ǝv������ł�����ǁA
�Ȃ����ƂĂ��Ȃ��ʓ|�E�E�E���Ă���������܂蒷���ēr���Ŏ��Ⴄ��������Ȃ��̂Œ��ԕ��Ƃ����Ƃ������R�ł��B
�i300���Ԓ��x�܂ł̉����ƁA�r���̕ω��ʁA���̌̂ł̃o�����̊ώ@�͌���lj��������ƍl���Ă��鎟��ł���܂��B���r���[���Ȃ��E�E�E�j
�ώ@���e�͖��x������݁A���g�������if�����j�ƁA�C���s�[�_���X�����ł���܂��B�i�������CLIOfw�g�p�j
�ώ@�̓h���C�o�[�P�̂ʼn���炵�āA10mm�̋����Ń}�C�N�ʼn������ϑ����Ă܂��B�i�}�C�N��Erthworks M30�A�w�b�h�z���A���v��m902�j
����͂�����ƋC��������ă}�C�N�̃O���[�h���グ�Ă݂܂����B
|
�y�R�D���萸�x�i�덷�j�ɂ��āz
���g�������ƁA�C���s�[�_���X�������e10�肵�A����덷���܂��ɐ��肵�܂����B
�{���͕W�������o�����N�[���ɂ��������Ƃ���ł����A�߂��ry
�E���g�������̑��萸�x�F�}0.2dB���炢�B
�E�C���s�[�_���X�̑��萸�x�F�}0.2�I�[�����炢�B
�E�E�E���ȁH�Ǝv���܂��B
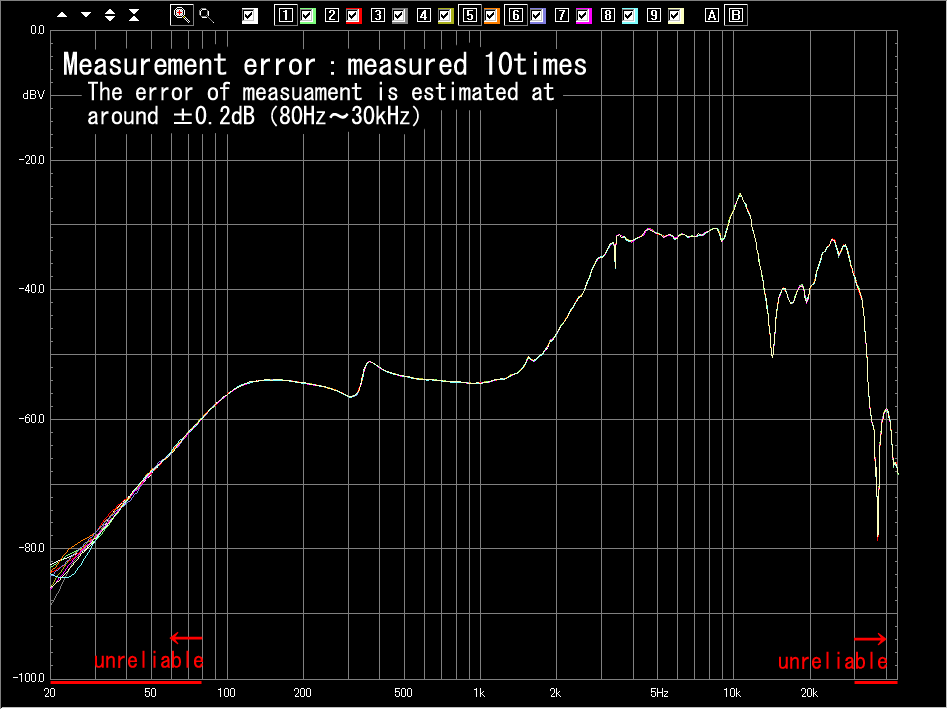 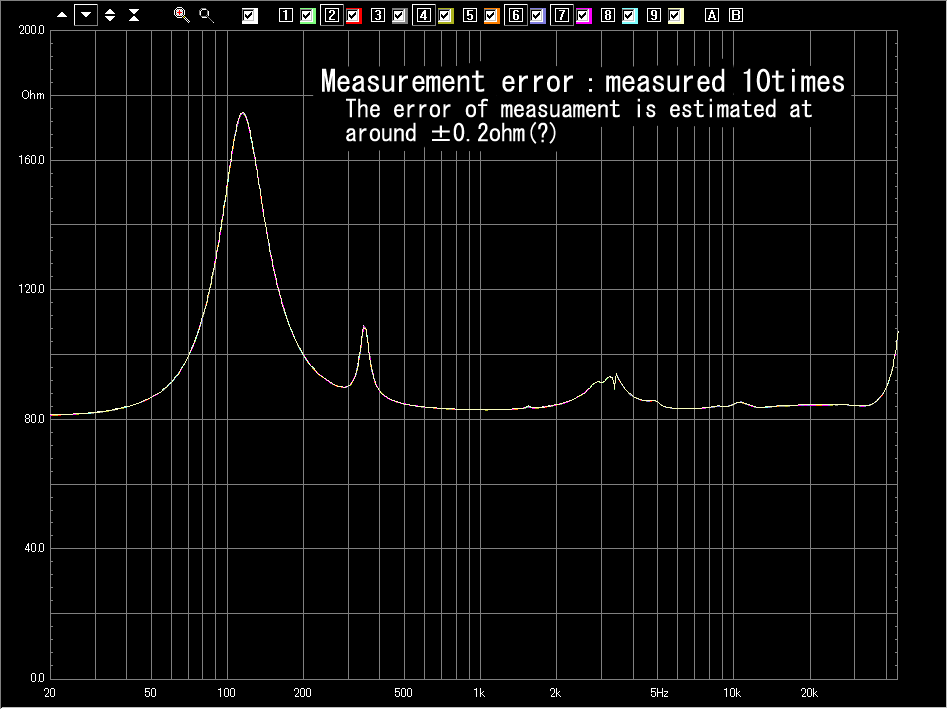 |
| �y�S�D����G�[�W���O�Ɏg���������ɂ��āz ���`�ƁE�E���ɍ�������܂��A �E��U�����o�����g���܂�ł��������A���U�������Ȃ�₷���낤�B �E�Ƃ͂����A�S�ш�ł���Ȃ�ɐU������������ł���B �E��`�g�A�T�C���g�A�z���C�g�m�C�Y�͂�����ƃJ���ɐG�鉹������C���B �E�E�E�Ƃ����A���v������ �u20Hz�̃T�C���h�{�s���N�m�C�Y�̍����g�v�i���}�́iC)�j���G�[�W���O�p�����Ƃ��č̗p���Ă݂܂����B �i�u�T�[�v���Ƃ���������ƉJ�����ۂ����ł��B�E�E�E�܂����邳�����Ƃɂ͕ς��Ȃ��ł����ǂ��B�j �܂��A�u�Ȃ�ƂȂ��E�E�E�v�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł�����܂����̂ŁA�������炸�B 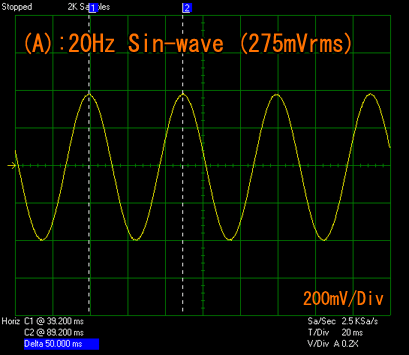 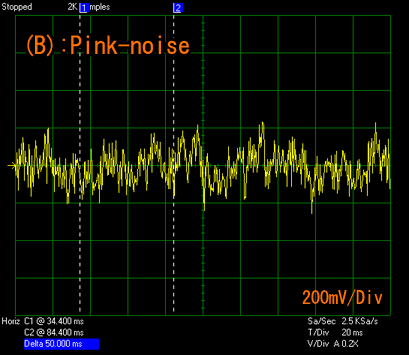 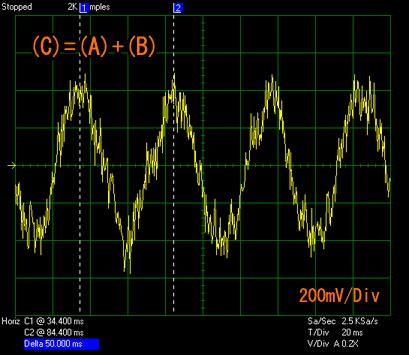 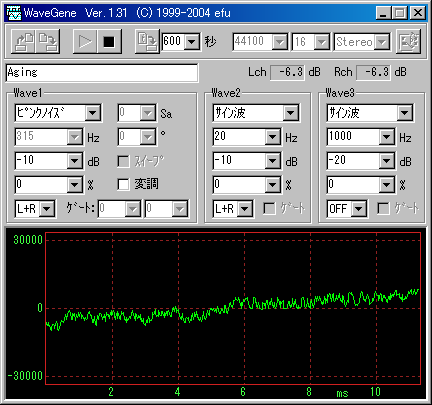 |
�y�T�D����̑��肵�����R�ƁA�����߂Ȃǁz
�����ς�炸�f�^�������������Ǝv���܂����A����ȂƂ���ɂ̓s�V�����Ɠ˂����݂���낵�����肢�������܂��E�E�E�o�����̓I���Ƃ��肪�����ł��B
�y���肵�����R�z
��^�̃w�b�h�z���ɂ��āA�G�[�W���O�̌��ʂ𑪂�ۂ̖��_�́A�e�ɂ��p�ɂ��u�s����ȃC���p�b�h����đ��肷��v���Ƃɂ�鑪�萸�x�̕s�����Ǝv���܂���B
�ߋ��ɊJ���^�̃w�b�h�z���ő���͂���Ă݂��̂ł����A��r�I���薈�̌덷�����Ȃ��J���^�ł��A�C���p�b�h����݂������A����Ő�dB���x�̑���덷�͔������Ȃ��B
����ł͓���G�[�W���O�̍��Ȃǂ킩��܂���B
���������킯�ō���̓h���C�o�[�P�̂ɂ��āA�u�h���C�o�[�P�̂̕������肪�V���v�������A�ϓ�����p�����[�^�����Ȃ����Ƃ���A���ω��̊j�S�ɂ��܂�邩���H�v�Ƃ����P�Ȃ�v�������ő����Ă݂��A�Ƃ������e�ł���܂����B
���ʓI�ɂ́A����̂悤�ɔ�r�I���������ȑ���ł��i�E�E�E�ƌ����Ă��A�[������������A�A�x���[�W���O�Ƃ������m�C�Y�팸�̑�͂��܂������E�E�E�j�A�h���C�o�[�P�̂��Ƒ���덷�́}0.2dB�ȓ��i�����������80Hz�ȉ��̓_���ł����ˁj�ɂ͊m�ۏo���Ă���悤�ł��B���̂��炢�̐��x������A�M���M�����ʂ͑���ł������ł��B
�Ȃ��u�����ƃn�E�W���O�֑g�ݕt���ĂȂ���Ԃł̓G�[�W���O�̌��ʂ͈���Ă���̂ł́H�v�Ƃ����w�E�͂������Ƃ��ł��B
�������Ȃ���A�h���C�o�[�P�̂̕����U���̔w�������|�I�Ɍy���A��芈���ɓ�����ԂɂȂ��Ă��锤�ł���܂��̂ŁA
�u�h���C�o�[�P�̂̕�����苭�͂ɃG�[�W���O�����v���̂Ǝv���܂��B�ł��̂ŐU���ɑ���G�[�W���O�̌��ʂ̍ő�l���ώ@����ɂ͕s�s���͖������̂ƍl��������ł��B
�y���茋�ʂ̉����߂Ȃǁz
����̊ώ@�̃i�]�ɂ��āA�����߂��ȉ��ɏ����Ă݂܂��B
�܁[�A�S�R�}�`�K�C��������Ȃ��ł����ǁB
MDR-900ST�̃h���C�o�[�́A�P��x���̃\�t�g�h�[���^�Ɨǂ������\�������Ă���A�G�b�W�i�^���W�F���V�����^�j�ƐU������̐��^���ꂽ���������q�ޗ��̂悤�ł��B�iPET�������H�j
�i�P�jfs���ω���AQ�l�̕ω����ɂ߂ď��Ȃ����R�ɂ��āF
�U���́u�G�b�W�iSURROUND�j�v�̃o�l����@�B��R�͖w�Ǖω����Ă��Ȃ����̂ƍl������B
�ω����ɂ������R�Ƃ��ẮA�ȉ��Q�_�ł͂Ȃ����H�Ɛ������܂��B
�@���E�h�X�s�[�J�[�̂悤�ȃ_���p�[�iSPIDER�j�������A�G�[�W���O�����Ώۂ̃T�X�y���V�����n�̓G�b�W�����Ȃ����A
�@���̃G�b�W�̓w�b�h�z���ł͐U���ƈ�̐��^����Ă���A���m�ȋ��E���Ȃ���r�I����ȏ�ԂƎv����_�B
�A�o�l����@�B��R�ւ̊�^�́A�G�b�W�����U���w�ʂ̋�C�̔䗦�������A�����G�b�W�̋@�B�I�ȓ������ω����Ă��e�������܂�傫���o�Ȃ������H�Ǝv����_�B
�Ȃ��A��ʓI�Ƀ��[�r���O�R�C���^�̃��E�h�X�s�[�J�[�ł́A�T�˃_���p�[���o�l����80���A�c��Q�O���̃o�l�����G�b�W�������Ă���Ƃ����Ă��邻���ł��B
�iLoudSpeaker Design CookBook 7th edition/Vance Dickson P.10�j
�Ȃ̂ŁA����a�̃��E�h�X�s�[�J�[�ɂ��ẮA�u���[�N�C���ɂ��fs�̒ቺ�i10%���x�ς�邱�Ƃ�����j�̌����Ƃ��ẮA�_���p�[�̏_�����ɂ���^���傫�����̂Ɖ������܂��B
�i�Q�j350Hz�ߕӂ̉����ω���50���Ԓ��x�ň�U�傫���Ȃ��āA100���Ԃ��z����Ƃ܂��������Ȃ��Ă��܂������R�F
�����s���B����͎����ɂ͌������J���i�C�ł��B�P�ɑ���n�̖�肩������܂��ʂ�����ɂ��Ă�350Hz�ߕӂŋǏ��I������悤�Ȉ�ۂł��B
�����͕�����Ȃ��ł����A350Hz�O��́i���Ȃ��Ƃ��h���C�o�[�P�̂ł́j�U�������b�L���O���[�V���������Ă���炵���Ƃ��날��A����Ȃ�ɕ��G�ȗv��������̂ł́H�Ɖ������܂��B
�Ⴆ�A�{�C�X�R�C���ƃM���b�v�̖��C�Ȃǂ��������肵�Ȃ��������H�Ǝv�����肵�܂��B�����[�����Ȋ��������܂��E�E�E�B����P�ɉ���ۂł����ǁB
�S�̓I�ɂ́u�ω��͋ɂ߂Ĕ����v�ƌ�������e���Ǝv���̂ł����A�����������Ȃ̂ŗ]�v�Ȃ��Ƃ�������܂��ʁB
|
�y�U�D�w�b�h�z���̃G�[�W���O�i�u���[�N�C���j�Ɋ��҂ł�����̂Ƃ͉�����H�z
���҂������ʂɂ��ẮA���E�h�X�s�[�J�[�̗Ⴊ�Q�l�ɂȂ邩���B
���E�h�X�s�[�J�[�ɂ�����A�u�G�[�W���O�v�u�o�[���C���v�u�u���[�N�C���v�Ƃ��Ă����̂́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂������ׂĂ݂�ƁA�ȉ��̂悤�ȋL�ڂ���B
�i�Q�l�ɂ��܂��������͂������B�j
�y���E�h�X�s�[�J�[�ƃw�b�h�z���̍\���̈Ⴂ�́H�z
���E�h�X�s�[�J�[�ł́A�X�`�t�l�X�i�o�l�̍d���ɑ����j��8�����x���X�p�C�_�[�������Ă���Ƃ̂��Ƃł���܂��B�i����2�j
����Œʏ�̃��[�r���O�R�C���^�̃w�b�h�z���̃h���C�o�[�́A�\�t�g�[�h�[���^�Ɨގ��̍\���ŁA�G�b�W�i�T���E���h�j�����ƐU����������̐��^����Ă�����̂��w�ǂ��Ǝv���܂��B
�X�p�C�_�[�ɑ�������p�[�c�͖����A�U�����g�̃G�b�W�Ńo�l���ƒ�R���������Ă���A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���B
�i�U���̌��̃v���[�g�Ƃ̊Ԃ���C���X�p�C�_�[�̑���H�Ƀo�l�^�_���p�[�̂悤�ɂȂ��Ă���E�E�E��������܂��ʂ��A����͎����͗ǂ��m��܂���B�j
�ȏ���A�w�b�h�z���ɂ��ăo�[���C���ʼn����ω�����\��������Ƃ�����A����͋��炭�u�U�����̂��́v�ƂȂ�܂��傤�B
�\�t�g�h�[���^�̂悤�ɋɂ߂Ĕ����_�炩���f�ނŕ����U�����邱�Ƃ�O��ɍ��ꂽ�w�b�h�z���̐U���ɑ��āA�G�[�W���O�̌��ʂ͂ǂ�ȕ��Ɍ����̂��H
�Ƃ����̂�����̊ϑ��̎��ł������܂ӁB
|
| �y�V�D�Q�l�ɂ��������z �G�[�W���O�iBreak-in�j�̌��ʂ�m�邽�߂ɎQ�l�ɂȂ邩������Ȃ������ł��B �Ȃ��A�J�b�R������A�F�̋����͉��ɂ����̂ł��B���݂܂���B |
| �����P TESTING LOUDSPEAKERS/Joseph D'Appolito P.17�@�uCHAPTER2 DRIVER TESTTING�v �� �u2.6.1 TESTING PRELIMINARIES�v �h���C�o�[�̃T�X�y���V�����͎g�p������Ɋɂ�ł����B�䂦�ɂ��́iT/S�j�p�����[�^�̓V�t�g���Ă��܂��B���̓_���l�����A�e�X�g�O�ɑS�Ẵh���C�o�[��broken-in����Ă��Ȃ���Ȃ�����B����́A�h���C�o�[�𒆋�ɒ݂邵�A�����ăp���[�A���v�ɂ����20�`25Hz�̎��g�������W�Ńh���C�u���邱�Ƃɂ���Đ�����������B���₩�ɃR�[�����ړ�����悤�h���C�u���郌�x�����Z�b�g���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�I�[�o�[�h���C�u���ʂ悤���ӂ��˂Ȃ�Ȃ��A�����Ȃ���X�s�[�J�[�ɕ����I�_���[�W�������炷�ł��낤�B �h���C�o�[��break in �ɂ͏��Ȃ��Ƃ�1���Ԃ�v����B |
| ����2 Loudspeaker Design Cookbook 7th edition/Vance Dickason P.195�@�uCHAPTER EIGHT�v���u8.20 BREAK-IN�v �e�X�g�ɐ旧���A�S�ẴX�s�[�J�[��broken in����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �������Ȃ���A������s��Ȃ��Ă͂����Ȃ����R�́A���Ȃ����z������قǂɂ͖��m�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B �啔���̃E�[�t�@�[�́A5����10���Ԃقǂ̊ԂɃT�X�y���V�����V�X�e�����u�_��Ɂv����邪�A�i�G���N���[�W���[�j�{�b�N�X�̐v�̂��߂ɗp����T/S�p�����[�^�[�ւ̌��ʂ͋ɂ߂ď��������̂ł���B �i�����F6.5�C���`�E�[�t�@�[���j�b�g��break-in�O��̃C���s�[�_���X���������l�ƁA���j�b�g�𖧕^����шʑ����]�^�̃{�b�N�X�Ɏ��߂��ۂ̑���ɂ��ăV�~�����[�V�����������g�������O���t�̐����A���B�j |
| ����3 �����Ǝ����@No.1035�@�i2009/5�����j P.144�@�u�u�b�N�V�F���t�^�o�X���t�G���N���[�W���[[�v��]�v���u���j�b�g��������̏����v���u(1)�G�[�W���O�v �i�����j100Hz�A2.83V�ŃG�[�W���O���s���������ω��ł��B�i�����j ���ۂ̕ω��ʂ́i�p�C�I�j�A���t�������W���j�b�gPE-101A��fs�ł���j100Hz�ɔ�ׁA�ifs�ቺ�́j3�`5Hz��Ƃ����킸���ł����B ���̏�30�����G�[�W���O����A�قږO�a���Ă��܂��܂��B �i�u���j�b�g�̃G�[�W���O�ɂ��Fs�̕ω��v�̃O���t�ƁA�u�G�[�W���O�ɂ��Fs�̕ω��v�̕\����B�j |
| �y�W�D�ʂ̌́i�V�i�j�𑪒肵�Ă݂�z�i2009/4/12�lj��j �F�X�Ƃ������Ă��܂���MDR-CD900ST�B ���͂⏉���̏�ԂƃY���������Ă��܂��Ă�����̂Ǝv���܂��B �����Łu���ʂ̏�Ԃ̃T���v���v�i�ȉ����Q�Ə����܂��j�Ƃ��āA�������CD900ST���w���������܂����B �E�E�E�ȂE�E�E���̂������{���]�|�̂悤�ȋC�����܂����A�߂����Ȃ邩��f�ɂ��ǂ��Ă͂����܂���B ��ŁA�܂��͂��́��Q�ɂ��āA���E�̃`�����l���̃}�b�`���O�̒��x�����邽�ߎ�n�߂ɃC���s�[�_���X�����𑪂��Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B �����Q���B�������������Ƃ����B ���ʁF 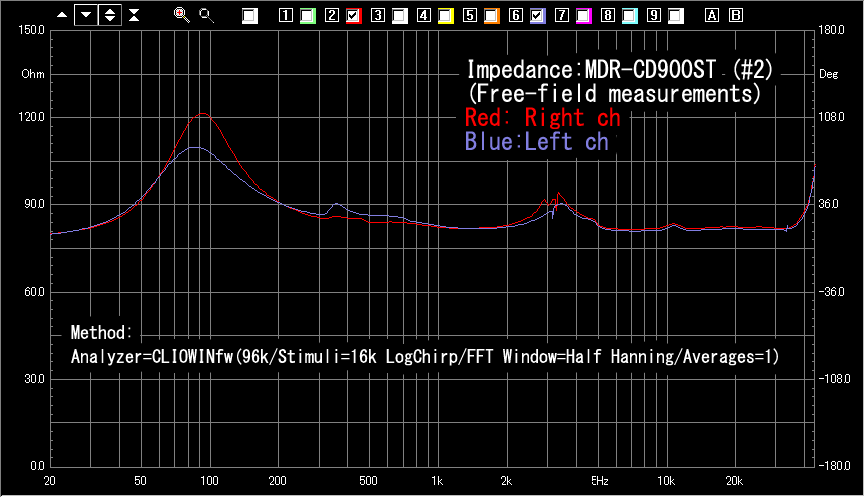 �E�E�E�E�E���߂����B �E�E�E�E�C����蒼���ƁA ���̃C���s�[�_���X�̈Ⴂ���͂����炭�́ABass-plug�̉�����R�̃Z�b�g�̋�̍��ł��傤�ˁB ��ch�Ɣ�ׂ�ƁA�Ech�̕����Z�b�g�̋���ɂ��悤�ł��B �����Ⴆ�Βቹ�̗ʂ�1dB���x�͈Ⴂ�����B �i���̃h���C�o�[�̃G�[�W���O���I����ă}�C�N�����瑪���Ă݂܂����B�j �[���Ƃ́A�ł� ����MDR-CD900ST�̌̂����Ɉُ�ȃT���v���łȂ��A���Ech�̂��̒��x�̍��͕��ʂł���Ƃ���A �G�[�W���O���������ƋC�ɂ��鐺�����Ă��ǂ������ȃ����ł����E�E�E �܂������������̂Ȃ̂ł��傤�B |
| �������� 2009/04/11�F�V�K�쐬 2009/04/12�F�y�W�D�ʂ̌́i�V�i�j�𑪒肵�Ă݂�z�lj� 2009/05/02�F�u���̌���炵�����A�G�[�W���O��500���Ԏ��{�������ʁv�lj� |
|